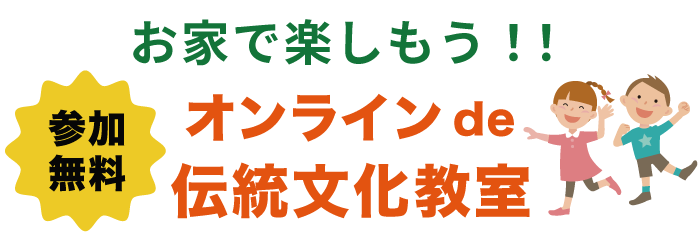時代の変化とともに、子供たちが、伝統文化等に触れ、体験する機会が少なくなっています。
長い歴史のなかで、大切に守り伝えられてきた「伝統芸能・生活文化」を、この機会にお子さまと楽しみませんか。
当イベントは、オンラインで、関西にゆかりのある伝統芸能や生活文化を、親子で楽しくわかりやすく学びながら、体験できるイベントです。
令和5年度は「大阪府の交野ケ原・交野節のおどり(かたのがはら・かたのぶしのおどり)体験」、「奈良県の奈良墨のにぎり墨作り(ならすみのにぎりすみづくり)体験」、「兵庫県のいけばな体験」、「神戸市の和ろうそくの絵付け(わろうそくのえつけ)体験」、「和歌山県の根來塗(ねごろぬり)体験」、「徳島県の阿波和紙の紙すき(あわわしのかみすき)体験」の計6体験です。
みなさんのご参加をお待ちしております!
注意とお願い
各体験で締切日が異なりますのでご注意ください。
また、当選通知が届いた後にキャンセルされる場合には、必ず事務局にご連絡くださいますようお願いいたします。
各体験の所要時間は、進行上の理由により、延長することがございます。予めご了承ください。

- 交野ケ原・交野節のおどり体験
- 大阪府
日程
- 令和5年11月11日(土)
時間
- 13:00〜
定員
- 40名
募集・当選スケジュール
募集は終了しました
- 募集開始 10月16日(月)
- 募集締切 11月8日(月)
当選者の方に教材として「踊りレクチャー冊子」をお送りいたします。
追加特典
「法被」&「万博音頭CD」もプレゼント!
現代の「河内音頭」の源流のおどり、万博音頭も披露!
現代の「河内音頭」の源流とも言われる「交野ケ原・交野節」は、大阪府の枚方市と交野市にまたがる交野ケ原で14世紀ごろに誕生しました。
南北朝時代、南朝方の楠正行(くすのき・まさつら)の軍勢が戦に敗れ、この地まで落ちのびた楠軍の軍師が、戦死した人を弔うために念仏踊りを行ったことが起源とも言われています。
交野節は、「七七・七五・七五」の字数を一つの節の単位として唄っていきます。そのため、この字数にあてはまるものなら、どんな物語でも唄うことができます。
保存会では、地元に伝わる伝説や名所・旧蹟・偉人伝等を題材にした新作も多く創作しています。
2023年には大阪府無形民俗文化財に指定されています。今回の体験では踊り方を教えてもらい、最後にみんなで楽しく踊る「万博音頭」を実際に踊っていただきます。
交野ヶ原交野節・おどり保存会

- 奈良墨のにぎり墨作り体験
- 奈良県
日程
- 令和5年11月11日(土)
時間
- 16:00〜
定員
- 40名

募集・当選スケジュール
募集は終了しました
- 募集開始 10月16日(月)
- 募集締切 10月30日(月)
- 当選発表 11月2日(木)
奈良墨の製法は数百年間ほとんど変わることなく続いています
墨の歴史は古く、およそ1400年前の西暦610年に奈良の飛鳥に伝えられたことが日本書紀の一節の中に記されています。その後、近畿地方を中心に国内での墨づくりが始まり発展していく中、現在の「油煙墨(ゆえんぼく)」と呼ばれる奈良市名産の墨が造られたのは今から約600年ほど前。今日まで奈良墨の製法は数百年間ほとんど変わることなく続いております。
今回の体験では実際に工房で作った墨をお送りして握っていただきます。握った墨は後日実際に使うことも可能です。
錦光園 長野睦


- 和ろうそくの絵付け体験
- 神戸市
日程
- 令和5年11月25日(土)
時間
- 13:00〜
定員
- 40名
募集・当選スケジュール
募集は終了しました
- 募集開始 10月23日(月)
- 募集締切 11月6日(月)
- 当選発表 11月9日(木)
お花の代わりとして描かれた絵ろうそく。現代ではインテリアとしてデザイン画や四季を描くなどあなただけのろうそくをお作りいただけます!
和ろうそくは室町時代に中国から渡来し、江戸時代に最盛期を迎えました。
明治以降は、西洋ろうそくの普及により減少の一途をたどっていましたが、ここ近年では、インテリアとしての『和の灯り』として人気を得ています。
今回の体験は、和ろうそくにオリジナルの絵付けをしていただきます。
和ろうそくkobe松本商店

- いけばな体験
- 兵庫県
日程
- 令和5年11月25日(土)
時間
- 16:00〜
定員
- 40名

募集・当選スケジュール
募集は終了しました
- 募集開始 10月23日(月)
- 募集締切 11月6日(月)
- 当選発表 11月9日(木)
いけばなってなーに?季節の花や草木などの植物を器に生けて、心の豊かさ、安らぎを求める伝統文化
私たち日本人は、古くから四季折々の季節を楽しんでいます。
日本の伝統文化である「いけばな」は、自然を愛する日本人の心がはぐくんだものです。
季節の木々や草花を器にいけることや、仏さまを敬って花をそなえるのもまた、日本人の習慣のひとつです。
今回は、お家で楽しく体験いただき、完成したらお家に飾ってみましょう。
兵庫県いけばな協会


- 根來塗体験
- 和歌山県
日程
- 令和5年12月16日(土)
時間
- 13:00〜
定員
- 40名
募集・当選スケジュール
募集は終了しました
- 募集開始 11月20日(月)
- 募集締切 12月4日(月)
- 当選発表 12月7日(木)
世の中に「~塗り」という呼ばれ方もない頃から「根來もの」として使われてきた伝統ある漆器
新義真言宗総本山根來寺で生まれた「根來塗(ねごろぬり)」。その特徴は丈夫さと形の美しさにあり、近世以降は下地の黒が見える朱塗りを根來塗と呼ぶほどに全国の産地に影響を与えました。使うほどにツヤが増し、下地に堅牢な漆下地を塗り重ねていることから鮮やかな朱色の下に中塗りの黒漆が浮かび上がり、味わいのある器へと変わっていきます。
今回の体験は、実際にうるしをぬっていただき、好きな模様を描いていただきます。
一般社団法人 根来塗振興会 伊藤惠

- 阿波和紙の紙すき体験
- 徳島県
日程
- 令和5年12月16日(土)
時間
- 16:00〜
定員
- 40名

募集・当選スケジュール
募集は終了しました
- 募集開始 11月20日(月)
- 募集締切 12月4日(月)
- 当選発表 12月7日(木)
徳島県吉野川市で作られている和紙!
阿波和紙は、和紙の伝統的な手法である「流し漉き」や「溜め漉き」という技法で作られています。
特徴は、手漉き(てすき)ならではの肌触りと、生成(きなり)の風合い。
そして、薄くても水に強くて破れにくい丈夫な紙質です。
今回の体験は、実際に紙すきミニ体験を行っていただき、阿波和紙を作っていただきます。
アワガミファクトリー 工藤多美子







当選者の方には、事前に体験セット等をお送りいたします。また体験内容によっては事前に準備していただきたい小道具などがございますので、本番までにご準備をお願いいたします。














その他ご不明な点がございましたら、
下記お問合せフォームよりお問い合わせください。

伝統文化親子教室の過去アーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。
伝統文化親子教室→『交野ケ原・交野節のおどり体験』
令和5年11月11日(土) 開催
『奈良墨のにぎり墨作り体験』
令和5年11月11日(土) 開催
『和ろうそくの絵付け体験』
令和5年11月25日(土) 開催
『いけばな体験』
令和5年11月25日(土) 開催
『根來塗体験』
令和5年12月16日(土) 開催
『阿波和紙の紙すき体験』
令和5年12月16日(土) 開催